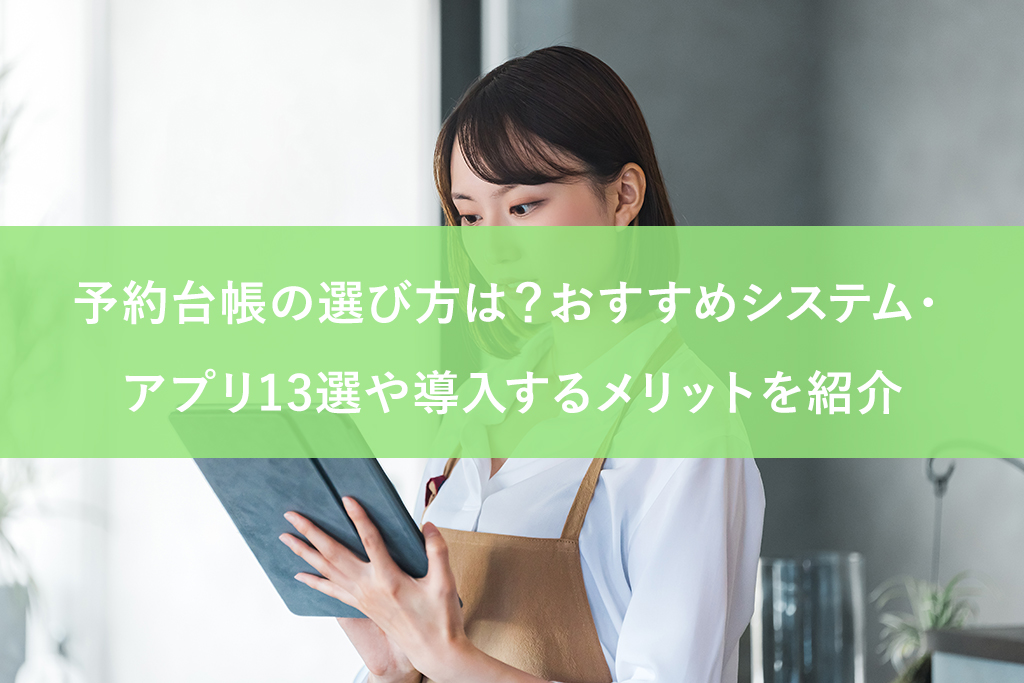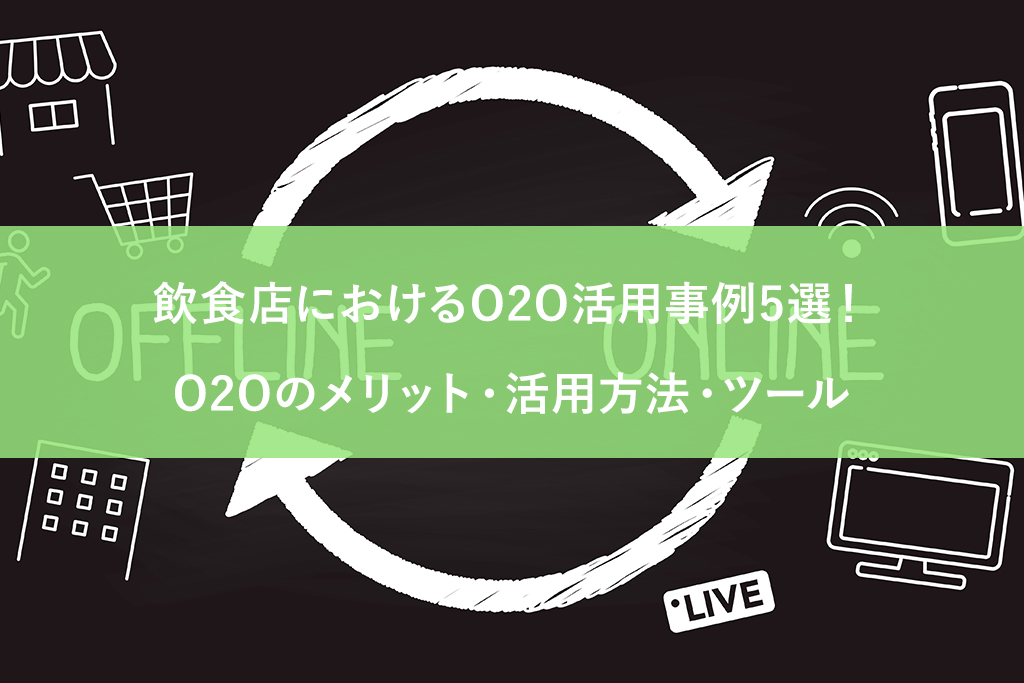
スマートフォンやSNSが広く普及している昨今、O2O(Online to Offline)マーケティングを取り入れている飲食店が増えています。
O2Oマーケティングは、オンラインからオフラインへと顧客を誘導することを目的としています。これにより、新たな顧客層へのアプローチや再来店の促進ができ、売上アップにつながります。
O2Oマーケティングに取り組むなら、まずはO2Oマーケティングの手法やツール、成功のポイントなどを知っておきましょう。
今回は、O2Oマーケティングが注目される背景やメリット、O2Oマーケティングの手法、成功のポイントなどを解説します。飲食店におけるO2Oマーケティング活用事例もあわせて紹介しますので、取り入れられるものがないかチェックしてみてください。
O2Oマーケティングとは

O2Oとは「Online to Offline」の略称で、オンラインからオフラインに誘導することを目的としたマーケティング施策のことです。
ホームページやSNS、お店アプリなどのオンライン上から、オフラインの実店舗などへユーザーを誘導し、来店・再来店につなげます。また、実店舗を訪れたユーザーをECサイトやお店アプリなどへ誘導するような、オフラインからオンラインへの誘導もO2Oに含めることもあります。
O2Oマーケティングの一例としては、次のようなものが挙げられます。
O2Oマーケティングの例
- SNSでセール情報を配信する
- 実店舗で使えるクーポンをアプリで配布する
- ECサイトで実店舗限定の商品を訴求する
- ポイントカードで再来店を促進する
O2Oは、インターネットが広く普及し、多くの人にとってスマートフォンやSNSが生活に欠かせないものとなった近年、注目を集めているマーケティング施策です。
O2Oマーケティングが注目される背景
O2Oマーケティングが注目される背景には、スマートフォンやタブレットの普及があります。消費行動が変化し、オンラインでの購買体験が身近になったことで、オンラインとオフラインの境目がなくなり、オンラインとオフラインを連携させて相乗効果を生み出すような取り組みが出てきました。
また、SNSが普及し、商品やサービスの口コミを手軽に共有できるようになりました。口コミを調べてから購入・利用する顧客が増えたことにより、オンラインでのマーケティングに力を入れることも、オフラインでの売上アップにつながっています。
オンラインでの消費行動が増えた一方で、商品を直接手に取れる、試着したり試食したりできるといった、実店舗ならではの購買体験も再評価されています。オンラインからオフラインへ誘導し、一貫したサービスを提供できる施策が求められているといえるでしょう。
O2OとOMO・オムニチャネル・マルチチャネルとの違い
O2Oと混同されやすいマーケティング用語に、「OMO」「オムニチャネル」「マルチチャネル」があります。それぞれの違いをみていきましょう。
O2OとOMOの違い
OMOは「Online Merges with Offline」の略で、オフラインとオンラインを融合することを指します。O2Oがオンラインからオフラインへの誘導をするのに対し、OMOはオンラインとオフラインの垣根をなくすことを目的としています。OMOはO2Oをさらに発展させた形といえるでしょう。
OMOの例としては以下のようなものが挙げられます。
- 店舗とオンラインショップの顧客データの一元管理
- 顧客データに応じたパーソナライズ化された戦略の立案
- アプリやスマートフォンで購入した商品を店舗で受け取れるサービスの展開
OMOの実施により販売機会の損失を抑えられるだけでなく、顧客体験の価値が向上し、LTV(顧客生涯価値)を最大化できます。
ただし、OMOに不可欠なデータベースなどの構築・活用には時間とコストがかかるため、長期的な視野で施策を実行できるような体制づくりが求められます。
O2Oとオムニチャネルの違い
実店舗やECサイト、SNS、アプリ、コールセンター、メール、広告など、企業と顧客との接点をチャネルと呼びます。オムニチャネルの「オムニ」とは、すべての(Omni)という意味であり、オムニチャネルはすべてのチャネルを統合・連携させることを指します。
顧客との接点が多様化するなか、接点のつながりを強化する(オムニチャネル化する)ことで顧客体験が向上し、販売機会の損失を防げます。
O2Oはオンラインからオフラインへの誘導を重視していますが、オムニチャネルはオンライン・オフライン問わずすべてのチャネルを活用しています。オムニチャネルの一環としてO2Oがあるとイメージするとよいでしょう。
O2Oとマルチチャネルの違い
マルチチャネルは、顧客が複数の異なる販売チャネルを活用できるようにし、接点を増やす販売戦略です。認知度向上や販売機会の増加などのメリットを得られます。
ただし、マルチチャネルではチャネル間でデータの共有・連携がされておらず、チャネルによって顧客が得られる購買体験には差があります。これらの問題を解消したものがオムニチャネルであり、マルチチャネルをオムニチャネル化することで、顧客に一貫性のある購買体験を届けられます。
O2Oマーケティングのメリット

飲食店がO2Oマーケティングを展開するメリットは、おもに次の4つです。
メリット
- 新たな顧客層にアプローチできる
- 効果測定がしやすい
- 再来店を促進できる
- 顧客利便性・満足度が向上する
新たな顧客層にアプローチできる
O2Oマーケティングを展開することで、新たな顧客層にアプローチできます。
チラシ配布やダイレクトメールなど、オフラインの販促では、アプローチできるエリアや人数が限られてしまいがちです。しかし、オンライン上で販促を行なえば、エリアや人数などの制約が生じることなく、多くの人にアプローチできます。
既存・顕在顧客だけでなく、お店や商品を認知していない潜在層にも情報を届け、実店舗に誘導できることはO2Oの大きなメリットです。
効果測定がしやすい
効果測定がしやすいこともO2Oのメリットの一つです。
例えば、アプリでポイントカードやクーポンを提供すれば、利用状況や利用率などをデータとして可視化できます。施策の良し悪しやお客さんの反応がわかるため、改善を図って施策の効果をさらに高めていくことが可能です。
再来店を促進できる
O2Oマーケティングは、オンラインで既存顧客にリアルタイムでアプローチできることから、再来店の促進に向いています。
例えば、お店アプリのプッシュ通知機能で実店舗の情報を配信したり、LINEやInstagramなどでフォロワー向けに実店舗で使えるクーポンを配布したりすれば、お店に足を運んでもらえるようになるでしょう。
O2Oマーケティングは、新規顧客の獲得だけでなく、既存顧客の囲い込みや再来店促進の効果も期待できます。
顧客利便性・満足度が向上する
O2Oは店舗だけでなく、顧客にも大きなメリットをもたらします。
例えば、実店舗と一体化したサービスとしてECサイトを提供したとします。すると、近くに店舗がない人や、営業時間外に買い物をしたい人もお店を利用できるようになり、顧客体験が向上します。
また、LINEやアプリなどを使って最新情報やクーポンなどを配信すれば、よりお得にお店を利用できるようになり、顧客満足度の向上が期待できます。
このように、O2Oには実店舗の顧客を誘導するという目的に加えて、顧客の利便性や満足度が向上するというメリットもあります。
O2Oマーケティングの課題
O2Oは新規顧客の獲得を得意としている一方、ファンの育成には向いていません。
例えば、実店舗への来客数を増やすためオンラインでクーポンを配布した場合、一時的に顧客は増えるかもしれませんが、その後の再来店の促進にはつながらないでしょう。O2Oの成果を次に活かすためには、再来店につなげる施策にも注力する必要があります。
また、O2Oの目的はオンラインからオフラインへの誘導であり、O2Oだけでは顧客単価は上がりにくいという特徴があります。顧客単価を更に上げるためには、OMOやオムニチャネルといった、オンラインとオフラインの垣根を超えた施策が必要です。
店舗の課題に合わせて、O2Oとその他の施策と組み合わせて実行することが大切です。
飲食店でO2Oを行なうための方法・ツール

続いて、飲食店がO2Oマーケティングを展開するためによく使われるオンラインツールを紹介します。おもなツールとその使い方をそれぞれ詳しく解説していきましょう。
方法・ツール
- ECサイト
- ホームページ・ブログ
- SNS
- お店アプリ
- ポイントカード・クーポン
ECサイト
飲食店がO2Oマーケティングに活用すべきツールの1つ目は、ECサイト(オンラインショップ)です。ECサイトを展開すれば、これまで立地や営業時間などの制約からお店を利用できなかった層を集客できます。
ECサイトでO2Oを展開する際のポイントは、サイト上で店舗の在庫状況を確認できるようにしたり、サイトで注文した商品を実店舗で受け取れるようにしたりと、実店舗と一体化したサービスを提供することです。
ECサイトと実店舗を別々に運営するのではなく、連携して運営することで、オンラインからオフラインへ、そしてオフラインからオンラインへの誘導がしやすくなります。
ホームページ・ブログ
ホームページやブログも、O2Oに使えるオンラインツールです。お店について調べている見込み顧客や、お店を利用したことがある既存顧客を実店舗へと誘導する場として適しています。
実店舗の魅力やお得情報、店舗を利用するにあたって必要な情報(住所や営業時間、アクセスなど)を記載しておくことで、オンラインからオフラインへと誘導することが可能です。
SNS
SNSもO2Oマーケティングの代表的なツールです。多くの利用ユーザー数を誇るLINEやInstagram(インスタグラム)、X(旧Twitter)などのSNSは、実店舗のセール情報や季節限定商品などを告知する場として適しています。
また、双方向のやり取りを通してファンの育成ができることもSNSの強みの一つです。実店舗に関する問い合わせに回答したり、予約を受け付けたりすれば、実店舗に足を運んでもらうきっかけを作ることもできるでしょう。
お店アプリ
お店アプリもO2Oをする上でよく取り入れられているツールです。お店アプリは、お店の集客・販促に特化した機能が集約されているため、実際に店舗を利用した顧客とオンラインでの接点を築き、再来店へとつなげることに適しています。
例えば、プッシュ通知でキャンペーン情報やセール情報を配信するなどして、再来店のきっかけを作り出すことが可能です。O2Oマーケティングから顧客情報の管理、効果測定までワンストップで行なえる点は、お店アプリの大きなメリットです。
お店アプリ制作サービスを徹底比較!主要サービスの機能・料金を比較
ポイントカード・クーポン
ポイントカードやクーポンの提供も、飲食店と相性が良いO2O施策です。ポイントカードやクーポンを提供することで、効果的に来店・再来店のきっかけをつくれます。
ECサイトや実店舗での購入に応じてポイントを付与しましょう。実店舗に来店するだけでポイントを貯められるデジタルポイントカードツールなどを導入し、顧客に利用してもらえば、「ポイントを貯めたい」というモチベーションから効果的に再来店を促せます。また、ポイントに応じて特典を付与すれば、さらなる再来店のきっかけを作ることが可能です。
店舗用ポイントカードアプリとは?作り方・アプリ化に役立つ便利なサービス
クーポンの展開も、ポイントカードと同様に効果的です。ホームページやSNS、アプリなどを活用して、実店舗限定のクーポンを配信することで、オンライン上の顧客を実店舗へと誘導できます。
位置情報
スマートフォンのGPS機能を活用し、顧客の位置情報をもとにして行なうO2O施策です。アプリを通して地域を絞ったセール情報やクーポンを配信したり、位置情報から一番近い店舗の予約できるようにしたりするなど、顧客にとってより身近な情報を提供できるようになります。
位置情報を活用したO2O施策は、実店舗が主要なチャネルである飲食店に向いています。
ただし、位置情報を活用するためには、当然、顧客に位置情報を提供してもらわなければなりません。プライバシーの観点から位置情報を提供しない設定にしている顧客も多いため、位置情報を提供することによって得られるメリットをいかに顧客に提示するかを考える必要があります。
QRコード
店頭やチラシ、DMにQRコードを記載してSNSアカウントへの登録やアプリのインストールなどを促すO2O施策です。この方法なら、オフラインからオンラインに誘導することが可能です。手軽に取り組みやすく、実際に多くの店舗で活用されています。
QRコードを導入することで顧客との接点を強化でき、シームレスな購買体験を提供できるようになります。
例えば、商品横に設置されたQRコードを読み込むことで、商品の詳細や口コミ、他店舗での取り扱い状況を確認できるようにしたり、ECサイトへ誘導して商品を自宅へ郵送できるようにしたりといったことが可能です。
また、QRコードをスキャンした顧客の情報をデータ化し分析することで、施策の効果測定やパーソナライズ化された施策の立案が可能です。定期的にクーポンを発行したり、お得な情報を発信したりすれば、再来店にもつなげられるでしょう。
O2Oマーケティングを成功させる3つのポイント
O2Oマーケティングを実行する際は、以下の3つのポイントを押さえましょう。
- 良質な顧客体験を提供する
- 複数の施策を並行して行なう
- O2Oマーケティングをサポートするサービスを導入する
良質な顧客体験を提供する
O2Oマーケティングによりオンラインからオフラインへ顧客を誘導できたとしても、オフライン(実店舗)での顧客体験が不十分だと、リピートにはつながりません。オンラインからオフラインへつなげる施策を実行するとともに、実店舗でしか味わえない良質な顧客体験を用意しておきましょう。
顧客がどのように商品やサービスを認知し、行動し、リピートするのか、体験の流れをふまえて、どのようなサービスを提供すれば良い顧客体験につながるのか改めて考えてみましょう。
複数の施策を並行して行なう
O2Oの施策が一過性のもので終わらないために、新規顧客の獲得とリピート促進を同時に行ないましょう。短期的な施策と長期的な施策を並行して実行することで、集客効果が長く続きます。
施策の向き不向きは取り扱う商品やサービスなどによって異なります。自社の長所や短所、競合との差異、用意できる資金や人的リソースなどをしっかりと分析したうえで、必要な施策を選択しましょう。
O2Oマーケティングをサポートするサービスを導入する
O2Oマーケティングに特化したサービスを導入すれば、O2Oマーケティングに関して自社に知見がない場合でも手軽に取り組めるようになります。サービス導入により専門家によるサポートも受けられるため、マーケティングの効果が早く出る可能性もあります。効果的に外部のサービスを取り入れましょう。
サービスを選ぶポイントは次項で詳しく解説していますので参考にしてください。
O2Oマーケティングをサポートするサービスを選ぶポイント

自社にO2Oマーケティングの知見がない場合や、時間や人的リソースを確保できない場合などには、O2Oマーケティングをサポートしてくれるサービスを活用しましょう。
サービスにはさまざまな種類があり、闇雲にサービスを導入してしまうと余計なコストがかかってしまう可能性があります。以下のポイントをふまえて、自社に最適なサービスを選択しましょう。
- 自社の課題を洗い出しておく
- 必要な機能・体制が整っているか確認する
- 定期的に効果を計測し改善する
自社の課題を洗い出しておく
サービスを選ぶまえに、まず、自社にどのような課題があるのかを確認しましょう。自社の課題とサービス内容を比較して、サービス導入によって課題が解決できると見込まれる場合にのみ、サービスの導入を検討しましょう。
課題の内容によっては、サービスを導入せずに自社内でO2Oマーケティングや他の施策を行なうほうが、費用対効果が高まる場合もあります。
必要な機能・体制が整っているか確認する
自社の課題をふまえて、サービスに何を求めるのかを明確にしましょう。必要十分な機能を持ち、利用料が予算の範囲内におさまるサービスを選ぶことがポイントです。オンラインコンテンツの連携機能、トラブルが発生した場合のサポート体制も確認しておくことが大切です。
また、O2Oマーケティングサービスを活用する際、ユーザーのデータを使用する必要がある場合があります。セキュリティ面が甘いサービスを使用してしまうと思わぬトラブルが発生する可能性があるため、セキュリティが充実しているサービスを選びましょう。
定期的に効果を計測し改善する
サービス導入後は定期的に効果を計測しましょう。課題の改善がみられない場合はサービスの利用停止や他サービスへの変更を検討しなければなりません。PDCAサイクルを回すことで自社の課題解決に向かっていけるようにしましょう。
サービスによっては効果をレポートにまとめてくれる場合もあります。レポート機能を活用すれば、データ集計の手間が省けるため、データを集計する時間がない場合は、レポート機能のあるサービスを導入しましょう。
飲食店におけるO2Oの活用事例
ここでは、上で紹介したツール・方法ごとに、飲食店におけるO2Oの活用事例を5つ紹介します。「具体的な活用イメージが湧かない」「同業の成功事例を参考にしたい」という方は、ぜひ参考にしてください。
- 俺の株式会社:ECサイト
- 100本のスプーン:ホームページ・ブログ
- 餃子の王将:SNS
- MeetFresh鮮芋仙:お店アプリ
- boulangerie Mure:ポイントカード・クーポン
俺の株式会社:ECサイト

公式サイト:俺のEC
「俺のフレンチ」や「俺のイタリアン」「俺の天ぷらバル」などのレストランを展開する俺の株式会社は、「俺のEC」というオンラインショップを運営しています。
レストラン店舗のように上質な食材を厳選し、リーズナブルな価格で販売を行なっています。湯せんなどの簡単調理で楽しめる商品や初めてセットを販売するなど、実店舗を利用したことがない顧客でも利用しやすいECサイトとなっています。
また、購入で獲得したポイントはECサイトと店舗の両方で利用できるなど、実店舗と一体化したサービスを展開している店も参考にしたいポイントです。
100本のスプーン:ホームページ・ブログ

公式サイト:100本のスプーン
ファミリーレストラン「100本のスプーン」は、訪れた人が実店舗に足を運びたくなるような魅力的なホームページを運用しています。
ホームページには、各店舗の様子や雰囲気、料理を楽しむお客さんの動画が掲載されており、実店舗に来店した際のイメージができるようになっているのが特徴です。店舗の魅力を動画で存分にアピールするという手法は、自社ホームページだからこそできる訴求方法でしょう。
ホームページを活用したO2Oを検討しているなら、ぜひとも参考にしたい事例です。
餃子の王将:SNS

続いて紹介するのは、SNSの活用が上手な中華料理チェーン「餃子の王将」のO2O事例です。
餃子の王将は、公式X(旧Twitter)アカウントでおもに新商品や季節限定商品の宣伝を行なっています。写真や動画を使って料理の魅力をビジュアル的にアピールしたり、実店舗で実施しているキャンペーンを告知したりして、近くの実店舗に足を運びたくなるような運用を行なっている点が特徴的です。
MeetFresh鮮芋仙:お店アプリ
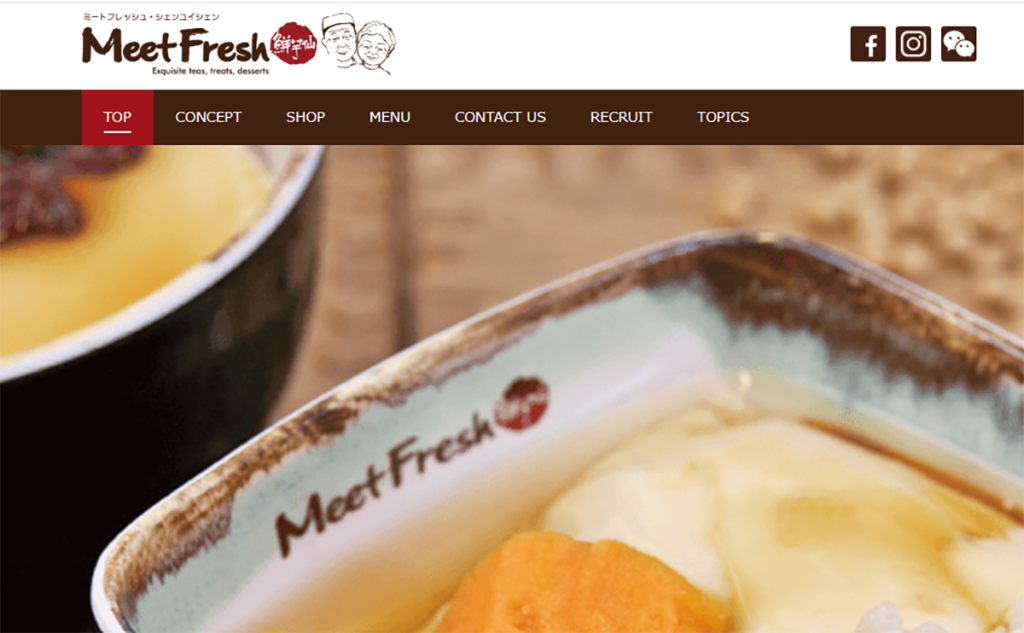
公式サイト:MeetFresh鮮芋仙
台湾スイーツ店「MeetFresh 鮮芋仙」は、お店アプリを導入し、リピーターや再来店の増加に成功しています。
同店は、お店アプリの導入をきっかけに、これまで実施していなかったスタンプカードを展開しました。スタンプ5個、10個、15個と段階に応じて特典を用意したところ、リピーターが増え、来客数の増加にもつながったそうです。
この事例からは、お店アプリは実店舗を訪れたユーザーをオンラインに誘導し、再来店を促進するO2Oにぴったりであることがうかがえます。
飲食店のO2Oには「常連コボットfor LINE」がおすすめ
飲食店におけるO2Oでは、実店舗にいかに足を運んでもらうかが重要となります。アプリやクーポンなどを通じて、継続的に顧客を呼び込める施策を実行しましょう。
O2Oに使用できるアプリにはさまざまなものがあり、サービス内容や価格が異なります。業界、業種によってアプリに求める機能は異なるため、飲食店のO2Oに最適なアプリを選ぶことが大切です。
当社ディップ株式会社でも、O2O施策に役立つ「常連コボットfor LINE」をご提供しております。
常連コボットfor LINEは、お店の常連客を獲得して売上アップを目指せるサービスです。国内で圧倒的な利用率を誇る「LINE」を使って、お店のポイントカードを作成できます。
LINEを使用するため、面倒なアプリダウンロードや会員登録は一切不要。初回来店時に、LINEを使ってポイントカード登録をしてもらうだけで、顧客とオンライン接点を築けます。
お客さんは「来店」「1日1回のログイン」「友だち紹介」でポイントをどんどん貯めて、貯まったポイントでクーポンを獲得できるため、オンラインからオフラインへ、効果的に再来店につなげられます。
また、ポイントカードをLINE公式アカウントと連携すれば、LINEトークにお店の宣伝を送ることもできます。オンラインで実店舗の情報やクーポンをリアルタイムに届けることで、さらなる来店促進が可能です。
常連コボットfor LINEは、最短1ヵ月で導入が可能です。これからのシーズンに向けてO2OやLINEを使った集客を検討中の飲食店経営者の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
「集客コボット for SNS Booster」なら飲食店のSNS予約連携が可能
近年ますますSNSの利用者が増え、飲食店の予約や検索のニーズがグルメサイトからSNSにシフトしてきています。O2Oを行う上ではずせないマーケティングツールと言っても過言ではなく、すでに運用をはじめているお店も多いでしょう。よりO2O施策の効果を上げて、飲食店の予約を増やしたいなら、SNSと店舗予約を連携できるサービスを導入してみましょう。
「集客コボット for SNS Booster」はGoogle MapsやInstagramに「席予約ボタン」を簡単に設置できるサービスです。国内だけなくインバウンドからの予約導線を設置でき、近年高まっているインバウンド需要にも対応できます。
また、集客コボット for SNS Boosterには、販促戦略に役立つレポート機能や予約台帳機能があります。
レポート機能では、予約経路別の予約実績や傾向を可視化できるため、どの予約経路に力を入れるべきかが一目でわかります。また、専用の予約台帳を利用するとホットペッパーグルメや食べログ、ぐるなびなどの外部グルメサイトの予約も一括で管理でき予約を素早く正確に把握できます。
初期手数料や予約手数料は無料ですので、予約が落ち込んでいて対策をとりたい場合や、予約管理システムを安く導入したい場合はぜひ集客コボット for SNS Boosterを導入してみてください。
インスタ集客力無料診断も受付中!
O2Oマーケティングは自社でもできますが、施策の方向性が本当に合っているのか、改善点はあるのかなどを自社内で判断するのは難しいものです。
集客コボットシリーズを提供するディップ株式会社では、飲食店様限定で「インスタ集客力診断」を実施しています。1,000店舗のInstagramアカウントを分析した結果をもとに、予約の入りやすさを診断します。
診断結果は評価をわかりやすくスコア化し、改善方法もお伝えいたします。診断は無料で実施できますので、Instagramの運用でお悩みの場合は、ぜひお気軽にお申し込みください。
【飲食店限定】 インスタ集客力 無料診断申し込みフォームはこちら
まとめ
オンラインからオフラインへ誘導するO2Oは、新規顧客にアプローチしたり、顧客の利便性や満足度を向上させたりするのに有用な手段です。
スマートフォンやSNSが人々の生活の一部となった今、来店促進にはオンラインからオフラインへの誘導が欠かせません。O2Oマーケティングは、アプリやLINEなどのSNS、ホームページなどのツールを上手に活用することで、より高い効果が期待できます。
今回紹介したツールやO2Oの活用事例を参考に、自店に合った方法でO2Oマーケティングを展開していきましょう。
飲食店の集客にお悩みの場合は、「常連コボットforLINE」「集客コボット for SNS Booster」の導入がおすすめです。コストを抑えながら効率的に既存顧客・新規顧客にアプローチできますので、ぜひ導入を検討してみてください。
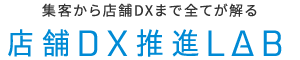

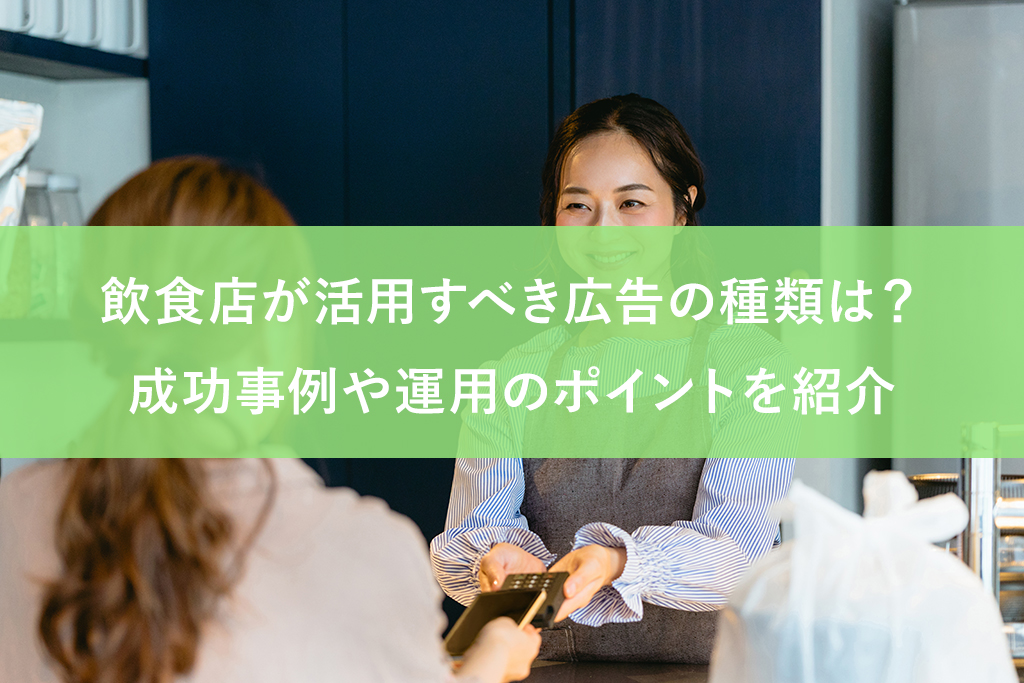


とは-1024x683.png)