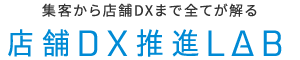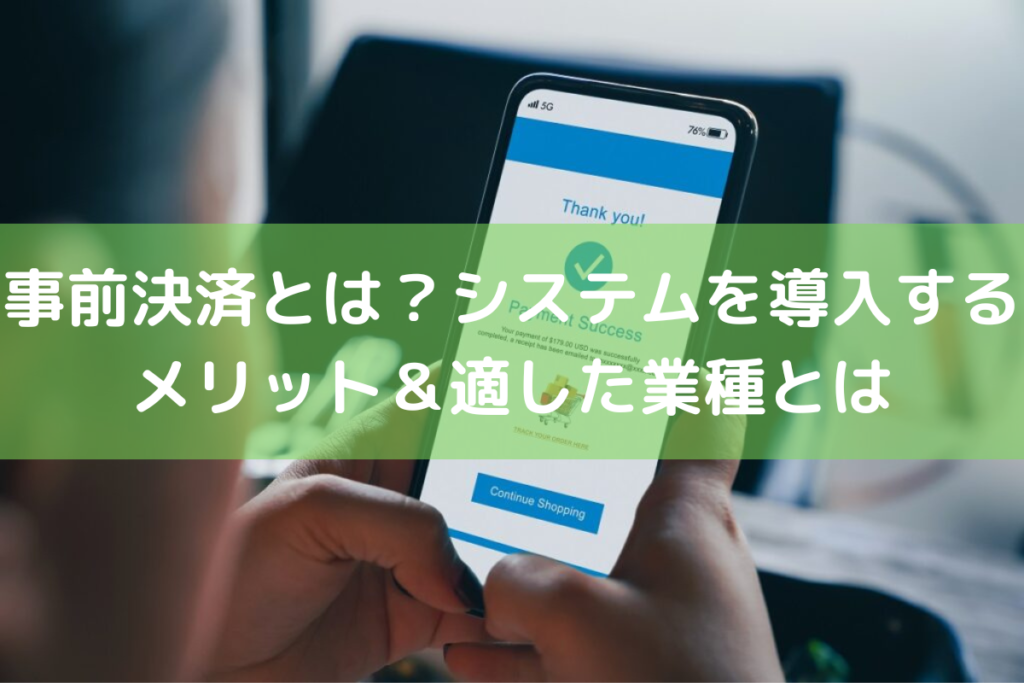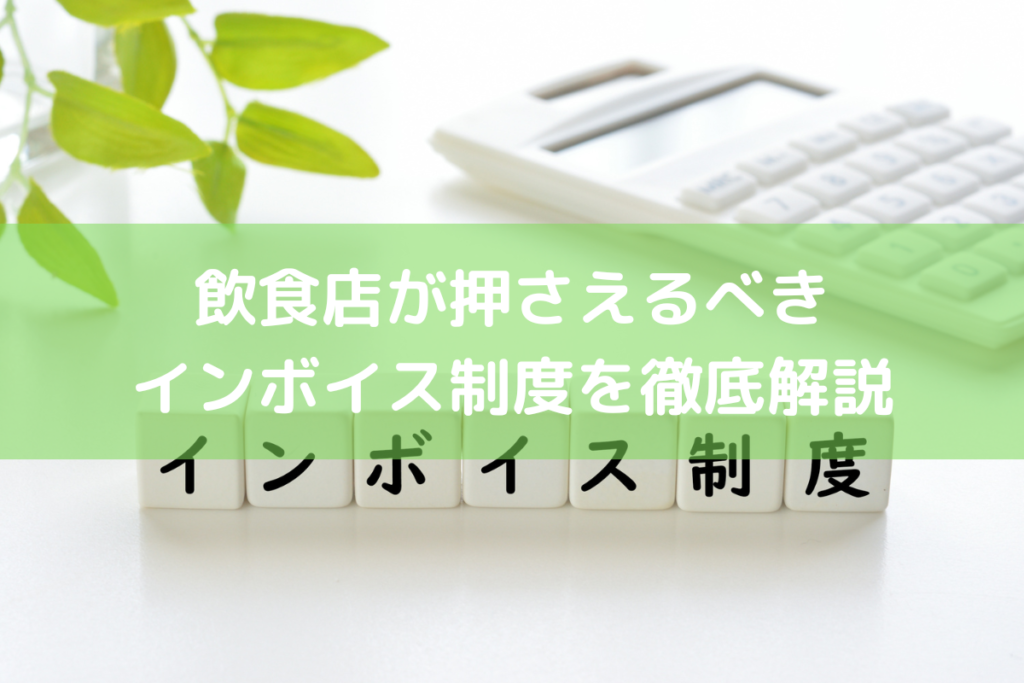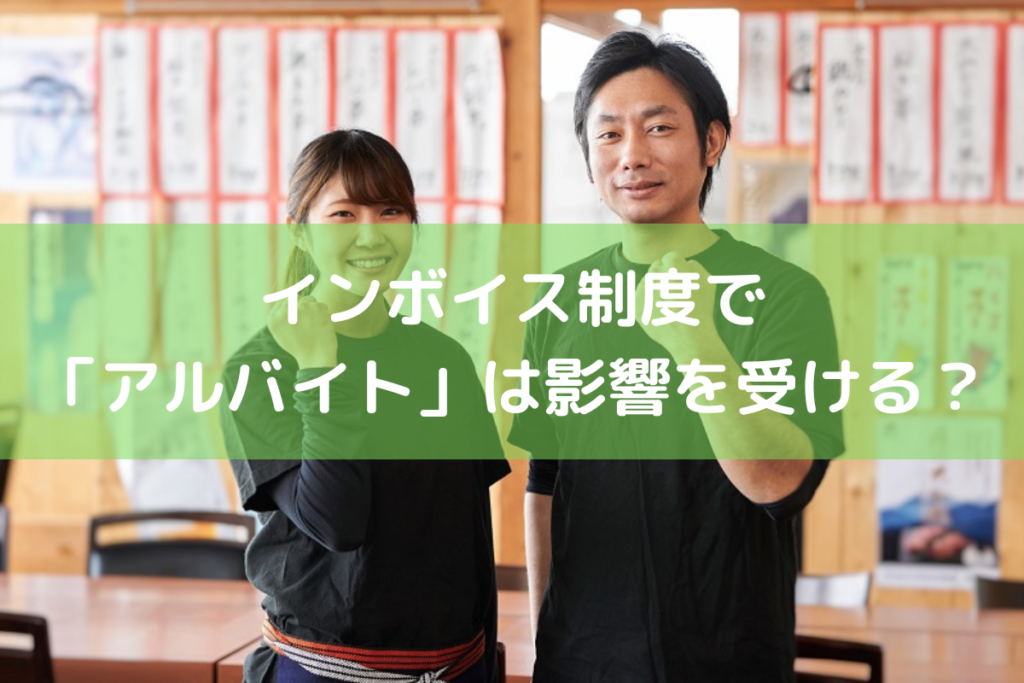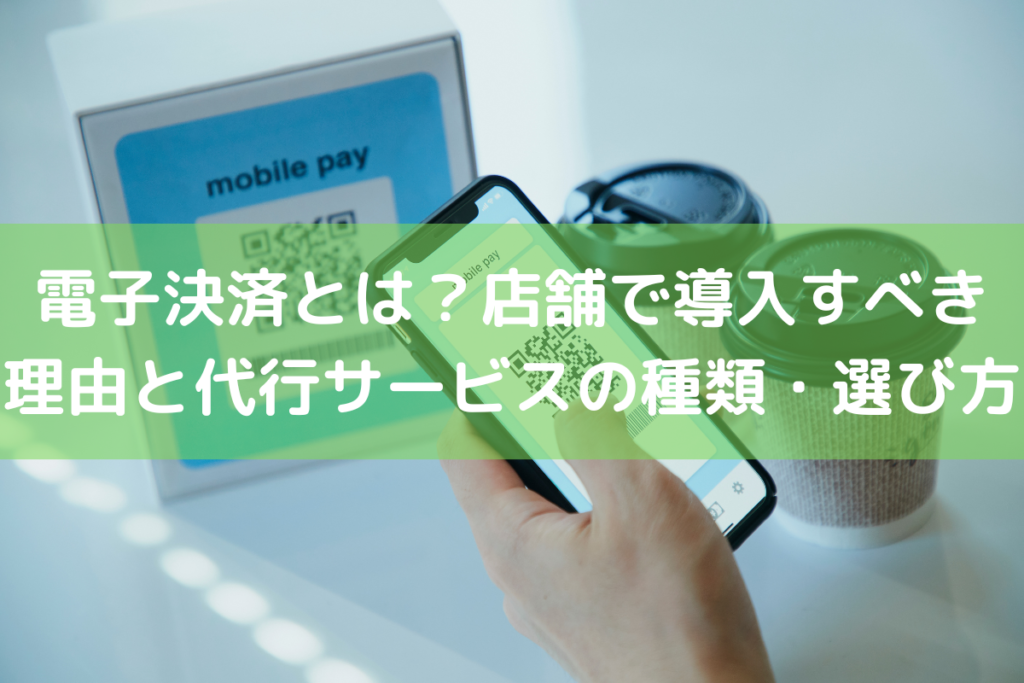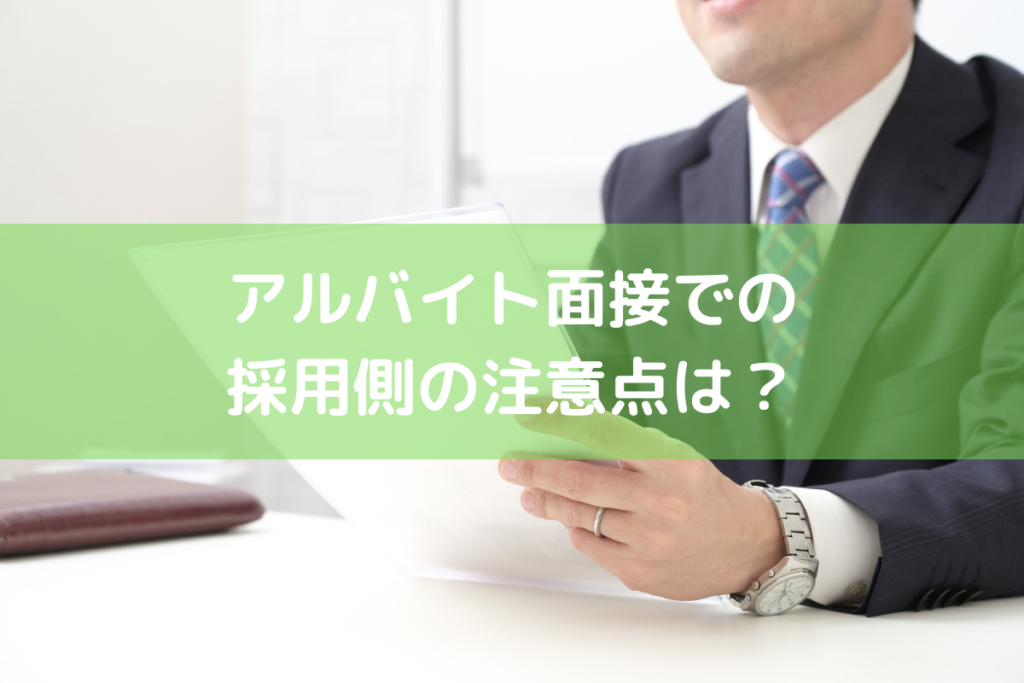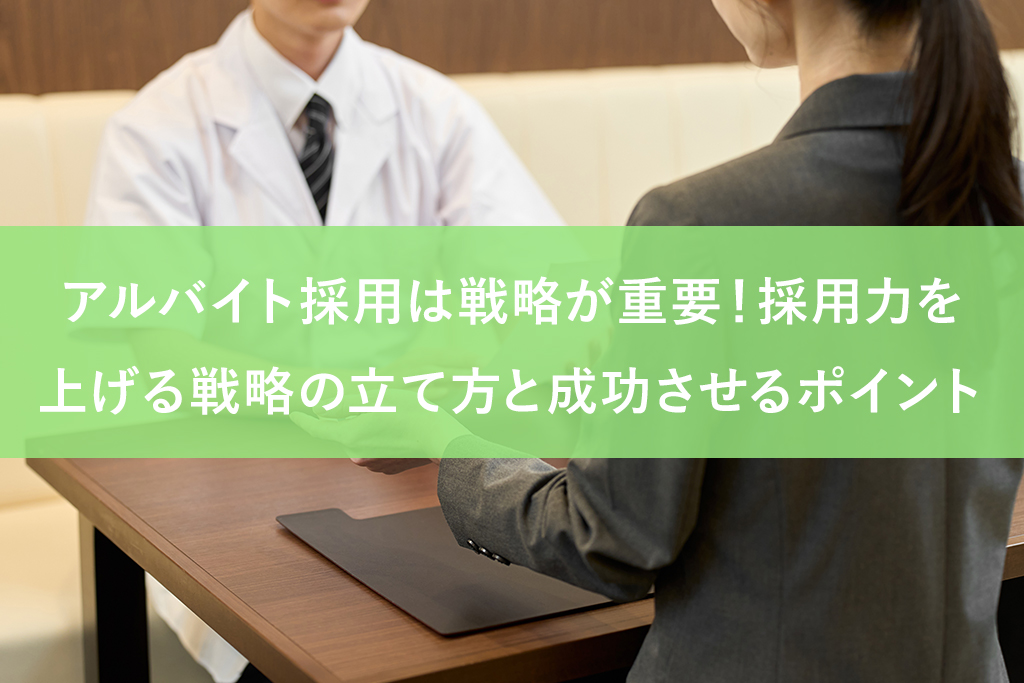
人手不足やアルバイトの採用難に悩む企業が増え続けている昨今、「なかなか応募が集まらない」「せっかく採用しても定着しない」といった課題に直面している方も多いのではないでしょうか。
人材が確保できないことで業務に支障が生じ、店舗の運営自体が困難になるケースも珍しくありません。こうした状況を打開するためには、やみくもに求人広告を出すのではなく、自社の現状やターゲットに合わせた採用戦略を立てることが不可欠です。
今回は、アルバイト採用が難しい現状とその背景、効果的な採用手法、採用力を高めるための具体的な戦略の立て方を解説し、採用後の定着率向上やコミュニケーションの工夫など、長く活躍してもらうためのポイントもご紹介します。
採用マーケットの現状
アルバイト採用が難しい理由を知る前提として、採用市場の現状について解説します。採用活動の難しさは、求人倍率という指標から判断できます。求人倍率とは、求職者1人に対して求人数がどの程度存在しているかを示す数値です。
2025年3月時点の全国平均有効求人倍率は1.26倍となっており、求職者1人に対して1.26件の求人がある計算です。前月よりもわずかに上昇していますが、地域によって差が見られ、東京都は1.12倍、大阪府は1.04倍と、都市部での求人倍率は1倍前後にとどまるケースが増えています。
参照元: 職業紹介-都道府県別有効求人倍率
「1人に対して1社であるなら、バランス良く就職できるのでは?」と思われるかもしれません。しかし、実際には人気の高い職種や条件の良い求人に応募が集中し、逆に不人気な業界や職種は慢性的な人手不足に陥る傾向があります。こうしたミスマッチが、採用活動の難易度をさらに高めているのです。
加えて、アルバイト市場のおもな担い手である学生層は、少子高齢化の影響で年々減少しています。求職者数が減る一方で、企業側の人材ニーズは高止まりしており、アルバイト採用の競争は激化している状況です。
アルバイト採用に苦戦する理由

アルバイトの採用に苦戦する理由は大きく分けて3つあります。
自社で採用がうまくいかないとお悩みの場合、何か理由があるはずです。思い当たる節がないか、採用市場を取り巻く背景、時代の変化、メディアの多様化など一つずつ確認していきましょう。
少子高齢化の影響
少子高齢化の進行は、アルバイト市場に深刻な影響を与えています。学生アルバイトの割合は減少傾向にあり、かつてはアルバイトの主力だった学生の姿が、以前ほど見られなくなってきました。ジョブリサーチセンターが行った「<学生版>求職者の動向・意識調査2023」
によると、2018年には70.0%だった学生のアルバイト経験率が、2023年には57.4%まで低下しています。
この学生アルバイトの減少は、飲食業やサービス業など、若年層の労働力に依存してきた業界に大きな打撃を与えています。これらの業界では、採用競争が激化し、慢性的な人手不足に陥っているのが現状です。
特に地方都市や郊外地域では、学生の絶対数が少ないため、アルバイトの確保はより困難な状況となっています。企業は、限られた人材を奪い合うだけでなく、高齢者や外国人労働者の活用など、新たな人材戦略を模索していかなければなりません。
インターネット・SNSの普及
インターネットやスマートフォンの普及により、世界のどこにいても働くことができるようになったり、企業について知ることができるようになったりしています。SNSを通して企業とやり取りをすることもできます。
こうした時代の変化が、求職者のアルバイト応募にも大きく影響しています。企業が発信していることだけではなく、口コミの投稿や一般人の呟きで意図せぬネガティブな印象を与えてしまうこともあります。
求人広告を見て求職者が応募する前に、ホームページや口コミ検索で評判を調べることは、もはや当たり前の行動になっています。
アルバイト採用に苦戦している企業のなかには、自社発信以外の原因が見つかる可能性もあります。自社にとってネガティブな書き込みや評判がないか、意識することも重要です。
求人手法の多様化
求人手法の多様化も背景の一つです。
1980年代以降、求人媒体や採用チャネルは時代ごとに進化し、現在ではインターネットやSNSをはじめ、さまざまな新しい採用手法が登場しています。このような採用手法の多様化により、企業は自社に合った最適な手法を選び、他社との差別化を図る必要性が高まりました。
しかし、求人手法が増える一方で、それぞれの特徴や効果を十分に理解しきれず、従来のやり方に固執してしまう企業も少なくありません。結果として、求職者とのマッチングが難しくなり、採用活動の難易度が上がっている状況です。
アルバイトの採用手法

アルバイト採用には、従来活用されてきた手法から、近年注目されている新しい方法までさまざまな選択肢があります。自社の採用ターゲットや募集状況に応じて、最適な手法を選ぶことが採用成功のカギです。ここでは、それぞれの採用手法についてご紹介します。
従来の採用手法
従来の採用手法には、おもに以下のようなものがあります。
- 求人広告
- ハローワークへの求人掲載
- 求人情報誌・折込チラシ
- 人材紹介会社の利用
- 地域コミュニティや学校への求人依頼
- 公共施設や駅・スーパーなどへの掲示
- 企業ホームページへの求人情報掲載
- 電話やFAXでの応募受付
それぞれ見ていきましょう。
求人広告
求人広告は、新聞や地域情報誌、インターネット媒体などさまざまなメディアで掲載が可能です。掲載費用や期間を柔軟に設定できるため、予算や募集人数に応じて最適なプランを選択できます。
特にインターネットの求人広告は、幅広い層へのリーチが可能で、即時性も高いのが特徴です。また、紙媒体の場合は地域密着型の募集に強みがあり、地元の求職者を集めやすいというメリットもあります。
ハローワークへの求人掲載
ハローワークは、無料で求人情報を掲載できる公的なサービスです。幅広い求職者に情報を届けられるため、コストを抑えつつ多様な人材を集めたい場合に役立ちます。特に地元で働きたい層や、安定志向の応募者を獲得しやすい点が特徴です。
手続きや掲載内容に一定のルールがありますが、公共性の高い採用チャネルとして根強い人気があります。
求人情報誌・折込チラシ
求人情報誌や新聞折込チラシは、地域密着型の募集に適しています。紙媒体ならではの手軽さがあり、特にインターネットに不慣れな高齢者層や、近隣住民への訴求力が高いのが特徴です。
生活圏内で目にする機会が多いため、地元の求職者にアプローチしたい場合に有効な手法です。
人材紹介会社の利用
人材紹介会社は、企業と求職者の間に入り、希望条件に合った人材を紹介するサービスを提供しています。成果報酬型が主流で、採用が決定した時点で費用が発生するため、無駄なコストを抑えられる点がメリットです。
短期間で即戦力となる人材を確保したい場合や、専門的なスキルを持つ人材を求める際に活用されています。
地域コミュニティや学校への求人依頼
地域コミュニティや学校への求人依頼は、地元の自治体や商工会、大学・高校などに直接求人情報を提供し、地域住民や学生にアルバイト募集を周知する手法です。学生や主婦層など、ターゲットを絞った募集に適しており、信頼性の高い人材を確保しやすいのが特徴です。
学校の掲示板やPTA、自治会などを通じて情報発信することで、地元で働きたい層への訴求力が高まります。
公共施設や駅・スーパーなどへの掲示
公共施設や駅、スーパーなど人が多く集まる場所に求人情報を掲示する方法は、地域住民への認知度向上に効果的です。通勤・通学途中の人々にも訴求可能であり、幅広い層にアプローチできます。コストも比較的抑えられるため、手軽に始められる採用手法の一つです。
企業ホームページへの求人情報掲載
自社のホームページに求人情報を掲載すれば、企業に関心の高い求職者を直接集めることができます。自社の魅力や働く環境をしっかり伝えられるため、ブランディング効果も見込める手法です。応募者とのマッチング精度を高めたい、あるいは長期的な採用活動を行ないたい企業に適しています。
電話やFAXでの応募受付
電話やFAXでの応募受付は、インターネットに不慣れな層にも対応できる伝統的な手法です。即時のコミュニケーションが可能なため、応募者の不安や疑問をその場で解消できる点にメリットがあります。特に高齢者層向けの募集や、地域密着型の採用に適しています。
新しい採用手法
従来の採用手法に加え、インターネットやSNSを活用した採用手法も広く浸透し、注目を集めるようになっています。
- 求人検索エンジン
- 求人サイト・Web求人媒体の活用
- SNSによる募集・情報発信
- 動画コンテンツによる職場紹介・募集
- デジタル広告
- ダイレクトリクルーティング
- チャットボットやLINE応募などの自動応答・応募受付システム
- オンライン面接・Web説明会・バーチャル採用イベント
- 短期・スポットバイトマッチングサービス
- 自社の人材プールを活用
- リファラル採用
それぞれ解説します。
求人検索エンジン
求人検索エンジンは、IndeedやGoogleしごと検索など、多数の求人情報を一括で掲載できるプラットフォームです。一般的には掲載無料から始められ、多くの求職者へリーチできる点に魅力があります。SEO対策を施せば自社の求人情報を上位表示させられるため、応募数の増加も期待できます。
求人サイト・Web求人媒体の活用
求人サイトやWeb求人媒体は、幅広い層へのアプローチに効果的です。掲載課金型や成果報酬型など、多様なプランが選べるため、予算や目的に合わせて柔軟に活用できます。また、詳細な企業情報や求人情報を掲載し、求職者に企業理解を深めてもらうことで、応募意欲の喚起にもつながるでしょう。
SNSによる募集・情報発信
SNSによる募集・情報発信は、InstagramやX、FacebookなどのSNSを活用して求人情報を発信する手法です。低コストで幅広い層に情報を届けられるのが特徴で、特に若年層へ向けたアプローチとして効果的です。
求人情報だけでなく、職場の雰囲気や社員の様子などを発信することで、求職者の共感を呼び、応募につながることも期待できます。ただし、継続的な運用と明確なターゲット設定が重要です。
動画コンテンツによる職場紹介・募集
動画コンテンツによる職場紹介・募集は、YouTubeやTikTokなどの動画配信プラットフォームを活用して、職場の雰囲気や仕事内容、スタッフの人柄などを伝える手法です。テキストや写真だけでは伝わりにくい社内の空気感や社員の表情、働く様子を直感的に伝達できるため、求職者の記憶に残りやすく、不安の解消や応募意欲の向上も期待できます。
また、動画はSNSや採用サイトで拡散されやすいことから、幅広い層へのアプローチや企業ブランディングにも役立ちます。
デジタル広告
デジタル広告は、インターネット上の検索エンジンやSNS、求人サイトなどに求人情報を掲載し、ターゲット層に効率良くアプローチできる手法です。地域や年齢、興味関心など細かな条件で配信先を設定でき、費用対効果が高いのが特徴です。
短期間で多くの求職者にリーチでき、採用活動のスピードアップにもつながります。
ダイレクトリクルーティング
ダイレクトリクルーティングは、企業側から求職者にコンタクトをとる攻めの採用手法です。企業が求めるスキルや経験を持つ人材をデータベースから探し出し、個別にスカウトすることで、ミスマッチが少なくなり、即戦力人材の獲得にも有効です。
専門性が高い人材の獲得や、採用競争の激しい業界において特に効果を発揮します。
チャットボットやLINE応募などの自動応答・応募受付システム
チャットボットやLINE応募などの自動応答・応募受付システムは、応募者からの問い合わせ対応や応募受付、面接日程調整などを24時間365日自動で行なう仕組みです。採用担当者が不在でも、チャットボットが応募者の質問に即時回答するほか、行動データの収集や面接の自動スケジューリングも可能です。
LINEなどのSNSと連携すれば、求職者は気軽に応募しやすくなり、企業側は業務負担の軽減が期待できます。大量応募や迅速な対応が求められるアルバイト採用現場で特に有効なシステムです。
オンライン面接・Web説明会・バーチャル採用イベント
オンライン面接・Web説明会・バーチャル採用イベントなど、インターネットを活用して場所や時間の制約なく採用活動を行なう手法も一般的になってきています。
ZoomやTeamsなどを活用したオンライン面接やWeb説明会は、遠隔地の求職者にも対応可能で、採用活動の効率化にもつながります。移動時間や場所の制約がないため、さらに多くの求職者にアプローチ可能なのがメリットです。
メタバースやVR技術を活用したバーチャル採用イベントでは、企業ブースの設置や社員との交流、職場見学の疑似体験など、リアルイベントに近い臨場感を提供できるのが強みです。
短期・スポットバイトマッチングサービス
短期・スポットバイトマッチングサービスは、1日や数時間単位など短期間・単発で働きたい求職者と、急な人手不足や繁忙期に対応したい企業をつなぐサービスです。企業は、スマートフォンアプリやWebサイトを通じて、必要な日時や条件を設定するだけで、希望に合ったワーカーと自動でマッチングできます。
求職者は履歴書や面接不要で即日勤務も可能なため、スキマ時間を活用したい方に人気です。企業側も、掲載無料・成果報酬型の仕組みで無駄なコストを抑えながら、急な欠員やシフト補充に迅速に対応できます。
自社の人材プールを活用
過去の応募者や退職者など、自社の人材データベースを活用し、再度アプローチする方法もあります。自社のことをよく理解している人材であれば、入社後のミスマッチが少なく、即戦力として活躍してくれる可能性が高いでしょう。
自社の人材プールを活用するには、定期的に人材データベースを整理し、スキルや経験をアップデートしておくことが重要です。
リファラル採用
リファラル採用は、現役スタッフや元スタッフからの紹介による採用手法で、定着率が高く、ミスマッチが少ないのが特徴です。企業の文化や価値観を理解している社員からの紹介であるため、企業との相性が良い人材が集まりやすい傾向があります。
紹介者にインセンティブを付与するなど、制度設計を工夫することで、より効果が高まります。
アルバイトの採用戦略はなぜ重要か
人手不足や応募者減少といった課題を解消し、企業の成長や安定した運営を実現するためにも、アルバイトの採用戦略は非常に重要です。戦略的な採用活動を行なうことで、採用コストの削減や従業員の定着率向上につながり、結果として企業ブランドの強化にもつながります。
特にアルバイトは、繁忙期や突発的な人手不足に柔軟に対応できる重要な戦力です。十分なアルバイト人材を確保できなければ、サービス品質の低下や既存スタッフへの負担増といったリスクが高まります。そのため、計画的かつ効果的な採用戦略を立てることが、安定した店舗運営や顧客満足の維持に直結します。
また、魅力的な求人戦略は企業のブランドイメージ向上や求職者の応募意欲アップにもつながります。アルバイト採用の質を高めることは、企業の持続的な成長を下支えする重要な要素といえるでしょう。
採用戦略の立て方

採用市場を取り巻く環境を把握したら、さっそく戦略を立てましょう。やみくもに求人広告を出したり、なんとなく振り返りを行なったりするのではなく、「〇〇をしたら■■が見込めるだろう」という仮説立てと検証を繰り返すことが重要です。
戦略の立て方についてプロセスを解説するので、一つずつ確認してみてください。
採用ターゲット・ペルソナを整理する
1つ目は、採用ターゲット・ペルソナを設定することです。
アルバイト採用の場合、期待するハードルが低く正社員よりもターゲット設定が甘くなりがちです。誰でも良いという求人広告は誰も集まりません。どのような人物が欲しいのか、整理していきましょう。
その際のポイントは次のとおりです。
・属性(学生・主婦・シニアなど)
・年齢や性別
・性格
・資格や経験
・応募の際に重視すること
こういった点を踏まえて、具体的に1人の人物がイメージできるくらい細かく考えてみましょう。
さらに重要なことは、ターゲットを1つに絞る必要はないということです。
「どうしても若い人でなければいけない」という凝り固まった考えを捨て、主婦層を獲得しにいったらすんなり採用ができたうえに、細かい配慮や温かみのある対応がプラスに作用したという話もあります。
ターゲットを3つくらい設定して、「自社と相性が良いのはどのような人材だろう?」というABテストを繰り返しても良いでしょう。正解のない求人活動だからこそ、こういった戦略が重要です。
採用計画を整理する
2つ目は、採用計画を作成することです。まずは過去の採用活動を洗い出して、1人採用するのにどのくらいコストがかかったのか計算してみてください。
例えば、10万円の求人広告を掲載して5人の応募、2人の採用ができたとします。その場合、応募単価は2万円で採用単価は5万円になります。
予算を決定するときにこの考えは非常に重要です。「なんとなく予算10万円」と決めるのではなく、想定応募や面接・採用数を割り出すと、計画的な予算管理をすることが可能です。
予算が決まったら、年間でいつの時期に何回募集をかけられるかイメージしましょう。トータルコストや採用目標人数を決めることで、先の見通しも立てやすくなります。
採用手法を選定する
3つ目は、採用手法の選定です。前段でも紹介したように採用手法は多様化しています。効率良く優秀な人材との出会いにつなげるためには、どのような手法・ツールを使用するかが大切なポイントです。
例えば、〇〇大学の1年生が欲しい場合は、次のような方法などが効果的です。
・サークルのSNSへ発信する
・新入生歓迎会にチラシを配る
・〇〇大学出身のスタッフが活躍しているという文言を広告に掲載する
ターゲットの生活や思考をイメージすることで、的外れなアプローチを防ぎ、よりリアルな手法を想像しやすくなります。ステップ1つ目で設定した具体的なターゲットは、ここで採用手法を決めるのに役立ちます。
複数のターゲットを狙う場合は、採用手法を組み合わせて決めていきましょう。それぞれの効果の違いを検証することで、自社との相性が良いターゲットが見えてきます。
応募後のプロセスを整理する
4つ目は、応募後のプロセスを整理することです。ここでのポイントは「面接をキャンセルされてしまう」「応募から面接日設定までに返信がなくなってしまう」という悩みが多い方にとって非常に重要です。
・応募から返信のスピード感
・電話対応の明るさ
・面接日前のリマインド連絡
など万全の体制が整えられているか振り返りましょう。
求職者は、複数社並行して応募をすることが多いため、競合他社よりも早く・印象良く・丁寧な対応が必須です。面接日の前日にはメールや電話で「明日の面接よろしくお願いします」という連絡を入れてみたり、番号を通知したメールを先に入れてから電話をかけてみたりといった工夫を積み重ねることで、誠実さは伝わります。
他のアルバイトスタッフにも協力してもらいながら、求職者を気持ち良く迎えられる環境を整備しましょう。
面接内容を整理する
5つ目は、面接内容の整理です。
面接は求職者の志望度を高められる唯一のチャンスです。面接中の姿勢・内容に問題はないでしょうか?
<基本的な面接の流れ>
・自己紹介
・志望動機
・履歴書を見て気になる点があれば質問
・仕事内容や働き方の確認
・質問受付
面接中、スマートフォンや時計を無意識に見たり、身体の向きが無意識に外向きになっていたりすることがあります。求職者は、面接官が自分に興味を持っているのか敏感に察知するため、大きくマイナスに働きます。
「なぜあんなに盛り上がったのに辞退されてしまうのだろう?」とお悩みの方は一度面接中の対応についてスタッフに見てもらうと良いです。自分にはわからない癖や課題が見つかる可能性があります。リラックスして話しやすい雰囲気を作りつつ、できるだけ紳士的な対応を心がけましょう。
採用戦略を成功させるポイント
計画した採用戦略を成功させるには、次の4つのポイントを押さえておきましょう。
採用力について理解する
1つ目のポイントは「採用力」です。採用力は造語ですので、明確な定義があるわけではありません。
ここでいう採用力とは、次のように分解することができます。
採用力=(企業としての魅力)×(募集条件)×(時期)×(募集媒体)×(応募対応)×(面接)×(内定者フォロー)
7項目を数値化したときに、どのくらいの数値になるのかをイメージするものです。
この項目は掛け算なので、どれか1つでも0の場合、採用力は一気に落ちます。
費用を多くかけて求人広告を掲載していても、面接対応が雑になってしまえば採用はうまくいきません。この場合、広告にさらに課金するよりも、面接フローを見直すことが優先されます。
逆に、企業の魅力が飛びぬけて良い会社は、他の数値が多少低くても採用に苦戦しないで済むかもしれません。採用力を高めるためには、それぞれの数値を上げる努力を行なうことが重要です。
また、採用力の考え方を理解することは、課題の抽出にも役立ちます。「今回の募集は時期が良くなかった」「企業力に頼って面接対応に時間を割けなかった」など振り返りの際に確認していく観点として参考にしてください。
自社の魅力について洗い出す
2つ目のポイントは、自社の魅力について向き合うことです。次の3点をメインに考えてみましょう。
・自覚している魅力
・相場と比較したときの魅力
・新しくプラスできそうな魅力
自覚している魅力とは、例えば「うちのお店は休みの日もBBQするくらい仲が良い職場」「シフト変更を希望しているスタッフがいたらみんなで積極的にカバーしている」といった自社の魅力のことを指します。なるべく細かく思い出して、他社との差別化を図ることが重要です。
相場と比較したときの魅力を知るためには、平均相場を知る必要があります。求人広告などの営業担当に伝えれば、平均時給や平均応募数などのデータをもらうことができるため、気軽に相談してみましょう。
相場と比較した際に、時給が高かったり働きやすい待遇が見つかったりすれば、アピールポイントになります。また、新しくプラスできそうな魅力とは、待遇を作り出すことです。
「もともと週5日のフルパートを募集していたけれど、応募数を増やすために週2日から勤務OKにしてみよう」という取り組みは大きなメリットになります。
魅力がなかなか見つからないという場合は、こうして待遇を新たに作り出すことも視野に入れてみましょう。3点を踏まえて自社のアピールポイントを見直すことで、広告や面接でのスムーズなアピールができ、優秀なアルバイト採用につながります。
アルバイトの育成方法について見直す
3つ目のポイントは、アルバイトの育成方法について見直すことです。採用活動に育成は直接関係ありませんが、アルバイトの採用が上手な企業は人を大切にすることができるため、採用活動もうまくいきやすいケースが多いのです。
さらに、研修制度が充実していることや、具体的に入社後のフローを面接時に説明することができるため、採用活動におけるメリットにもなりやすいです。
アルバイトの業務内容はシンプルで簡単にできる作業が多いです。だからこそ、「どのように簡単なのか?」「何ができれば昇給できるのか?」について説明できるとよいでしょう。
効率良く人材を補充していくためには、長く働いてくれるスタッフを育てるという観点も忘れてはなりません。
SNSを活用する
4つ目のポイントは、SNSの活用です。
スマートフォンの普及により幅広い世代にとってSNSは身近な存在となりました。気軽に発信・拡散ができるSNSは、採用活動にも役立ちます。
企業の情報・募集条件・職場の雰囲気・スタッフの声などを発信することで「ここで働きたい」というエンゲージメントを高めることも可能です。
Twitterは、140文字の呟きが気軽で、拡散力が高いという強みがあります。Instagramは、写真やショート動画といったビジュアルで若者層にアプローチできます。Facebookは、中高年をメインにつながりを持つことができます。YouTubeは、動画を通して一番リアルを伝えることができます。
それぞれの媒体の特性を活かして、リーチしたいターゲット層にアプローチしていくことが重要です。求人広告や採用ホームページよりもリアルタイムな情報を継続して発信していくことができるので、積極的に活用していきましょう。
時期とトレンドを把握する
5つ目のポイントは、採用ターゲットが活発に動いている時期と、落ち着く時期を把握して活動することです。たいていは、ターゲットに関連するイベントにリンクするケースが多いです。
<大学生>
・授業の抽選が終わったあと
・長期休暇中
・長期休暇後でお金がない時期
・就活が終わったあと
<主婦>
・子どもの長期休暇明け
・新生活や新学期スタートのあと
大学生は学校に合わせることが多く、主婦は夫や子どもの予定に合わせることが多いです。こういった時期を狙って採用活動をすることが重要です。また、コロナ禍や災害など特別な動きがあるときにも慎重に見極めましょう。
競合の数が少ないタイミングに先手を打つと考えるか、ターゲットの動きが最も活発な時期に活動するかで結果は大きく異なります。欠員が発生してから慌てて対応するのではなく、あらかじめ不測の事態に備えていきましょう。
アルバイトの採用で成功するには「定着率」アップも大切

アルバイト採用に力を入れることはもちろん重要ですが、採用できてもすぐに辞められてしまっては、時間もコストも無駄になってしまいます。実際に、「せっかく採用したのに、すぐに辞めてしまう」「なかなか人が定着しない」という悩みを抱えている企業は多いのではないでしょうか。
アルバイトの定着率を高めるためには、「この職場でずっと働きたい」と思ってもらうことが大切です。そのためには、給与や待遇だけでなく、職場の雰囲気や人間関係、キャリアアップの機会など、さまざまな要素が重要になります。アルバイト一人ひとりの個性や希望を尊重し、働きがいのある環境を提供することが、定着率向上につながります。
また、アルバイトとのコミュニケーションは、定着率を向上させるうえで欠かせません。日頃から積極的にコミュニケーションを取り、アルバイトの意見や不満に耳を傾けることで、信頼関係を築けば、働きやすい職場環境が実現できます。定期的な面談やアンケートなどを実施し、アルバイトの声を反映させることも有効です。
「バイトルトーク」でコミュニケーションを円滑化しよう
「バイトルトーク」は、現場の連絡やシフト調整などアルバイトとのコミュニケーションを円滑化し、安心・安全な職場環境を実現するための新しいバイト連絡用アプリです。
従来は個人のSNSを使った連絡が主流でしたが、情報漏洩やハラスメント、プライベートとの混同といったリスクがつきものでした。「バイトルトーク」は、こうした課題を解決し、業務とプライベートをしっかり分けた連絡環境を実現できます。
アプリ内では、チャット機能による1対1やグループでの連絡はもちろん、シフト提出や調整もタッチ操作で簡単に完結。提出されたシフトは自動で一覧化され、未提出者へのリマインドや、急なシフト交代依頼もワンタッチで対応可能です。掲示板・お知らせ機能を使えば、全員への情報共有もスムーズに行なえます。
バイトルトークを導入することで、連絡やシフト調整の手間を大幅に削減できるだけでなく、コミュニケーションの質が向上し、アルバイトの定着率アップにもつながります。
まとめ
アルバイト採用を成功させるためには、現状の採用活動を見直し、戦略的に取り組むことが不可欠です。ターゲットの明確化や採用手法の多様化、応募者との円滑なコミュニケーションを意識することで、コスト削減や長期的な人材不足の解消、定着率の向上につながります。
応募者とのやり取りやシフト調整、情報共有の効率化を図るには、専用アプリ「バイトルトーク」の導入がおすすめです。
バイトルトークでは、アルバイトのシフト提出や調整、掲示板でのお知らせ配信まで一括管理が可能。従来の個人SNSの利用によるリスクを回避しつつ、業務連絡の効率化と職場の定着率アップを実現できます。今後の採用活動をより効果的に進めるためにも、ぜひバイトルトークの活用を検討してみてください。